訪問看護を生活保護の受給者が利用するには?利用条件や費用負担について解説
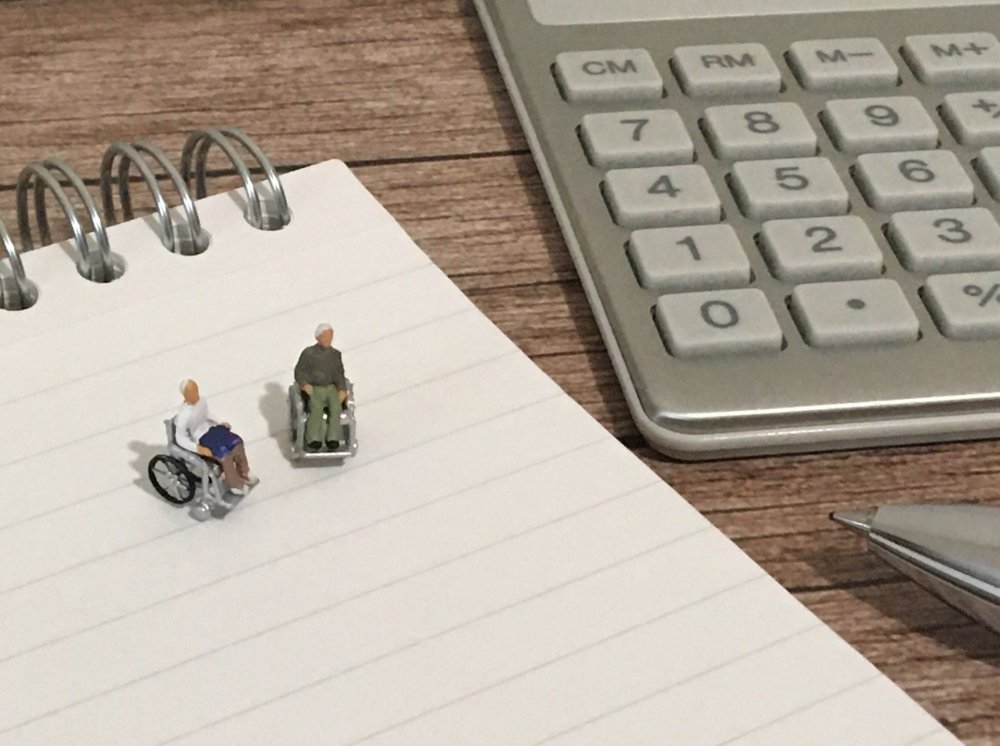
生活保護を受給されている方が、安心して療養生活を送るために、訪問看護は重要な役割を果たします。この記事では、生活保護受給者が訪問看護を利用するための条件や流れ、料金についてわかりやすく解説します。「訪問看護」と「生活保護」に関する疑問を解消し、必要な支援に繋がる一助となれば幸いです。
目次
- 生活保護受給者が訪問看護を利用するには
- 訪問看護を利用できる条件
- 訪問看護の利用の流れ
- 生活保護受給者の訪問看護料金
- 訪問看護の回数と時間
- 訪問看護に関する注意点
- 指定医療機関とは
- 指定医療機関の探し方
- 受診時の注意点
生活保護受給者が訪問看護を利用するには
訪問看護とは
訪問看護とは、看護師や理学療法士などの医療従事者が、自宅で療養する方の家を訪問し、看護やリハビリテーションを提供するサービスです。病気や怪我、障がいなどにより通院が困難な方、自宅での療養を希望される方が利用できます。具体的なサービス内容は、病状の観察、服薬管理、創傷処置、排泄の援助、リハビリテーションなど、利用者の状態やニーズに合わせて多岐にわたります。訪問看護は、医療保険または介護保険を利用して受けることができます。生活保護を受給されている方は、原則として医療扶助により訪問看護を利用できます。
生活保護における医療扶助
生活保護制度における医療扶助は、被保護者の医療に必要な料金を給付する制度です。病気や怪我の治療に必要な医療サービスを受けるための料金が対象となり、訪問看護もその一つです。生活保護受給者が訪問看護を利用する場合、原則として自己負担はありません。医療扶助により、訪問看護の料金が全額支給されます。ただし、医療扶助を利用して訪問看護を受けるためには、いくつかの条件を満たす必要があります。具体的には、医師の指示書が必要であることや、指定医療機関でサービスを受けることなどが挙げられます。
訪問看護を利用できる条件
医療保険と介護保険の違い
訪問看護は、医療保険と介護保険のいずれかを利用して受けることができます。どちらの保険が適用されるかは、利用者の年齢や病状、介護度などによって異なります。
| 区分 | 医療保険 | 介護保険 |
| 対象者 | 年齢に関わらず、病気や怪我などで治療が必要な方 | 65歳以上で介護保険の認定を受けた方、または40歳以上64歳以下で特定疾病により介護保険の認定を受けた方 |
| サービス内容 | 病状の観察、服薬管理、創傷処置、リハビリテーションなど、治療を目的とした医療行為が中心 | 食事、排泄、入浴の介助、リハビリテーションなど、日常生活の支援を目的とした介護サービスが中心 |
| 利用限度額 | 原則として、医療費の自己負担割合(1~3割)に応じて料金が決まる(生活保護受給者は医療扶助により自己負担なし) | 介護度に応じて利用限度額が設定されており、限度額を超えた場合は自己負担が発生する(生活保護受給者は原則として医療扶助により自己負担なし) |
医療保険と介護保険についてはこちらでも解説しております。ぜひご確認ください。
訪問看護で医療保険が適用される条件とは?介護保険との違いも解説!
介護保険で訪問看護を利用するには?サービス内容と費用を徹底解説!
生活保護受給者の場合、原則として医療保険が優先されます。しかし、介護保険の対象となる状態であれば、介護保険を利用して訪問看護を受けることも可能です。どちらの保険を利用するかは、医師やケアマネジャーと相談して決定します。
医師の指示書が必要な場合
生活保護受給者が訪問看護を受けるためには、原則として医師の指示書が必要です。医師の指示書とは、患者の状態や必要な看護内容を医師が記載した書類で、訪問看護ステーションは、この指示書に基づいて訪問看護計画を作成し、サービスを提供します。指示書には、訪問看護の目的、期間、具体的な看護内容などが記載されます。
ただし、緊急の場合や、介護保険を利用する場合は、医師の指示書がなくても訪問看護を受けられる場合があります。詳しくは、地域の福祉事務所や訪問看護ステーションに相談してください。
訪問看護の利用の流れ
生活保護を受給されている方が訪問看護を利用する場合、いくつかのステップを踏む必要があります。ここでは、相談窓口の紹介から、申請方法、訪問看護ステーションの選び方まで、具体的な流れを解説します。
相談窓口
訪問看護の利用を検討する際、まずは相談窓口に相談することが大切です。相談窓口では、訪問看護に関する様々な情報提供やアドバイスを受けることができます。主な相談窓口としては、以下のものが挙げられます。
- 福祉事務所: 生活保護を担当する福祉事務所は、訪問看護の利用に関する相談も受け付けています。生活保護受給者の状況を踏まえ、適切なアドバイスや手続きのサポートを受けることができます。
- 地域包括支援センター: 高齢者の方やその家族を対象とした相談窓口です。介護保険サービスだけでなく、医療保険を利用した訪問看護に関する相談も可能です。
- 訪問看護ステーション: 直接、訪問看護ステーションに相談することもできます。サービス内容や料金、利用条件など、具体的な情報を得ることができます。 私たち「訪問看護ステーションおうちナース プリュム」でも相談を受け付けています。下記からぜひご連絡ください。 訪問看護ステーション おうちナースプリュム お問い合わせ
これらの窓口では、利用者の状況や希望に応じて、最適な訪問看護サービスを提案してくれます。また、申請手続きや必要な書類についても詳しく教えてもらえます。
申請方法と届出が必要な書類
生活保護受給者が訪問看護を利用する場合、原則として医療扶助による給付を受けるために、申請が必要です。申請の流れは以下の通りです。
- 医師の診察: まずは、かかりつけ医に訪問看護が必要である旨を伝え、診察を受けます。
- 指示書の交付: 医師から訪問看護指示書を交付してもらいます。指示書には、訪問看護の必要性や具体的な指示内容が記載されています。
- 福祉事務所への申請: 指示書を持って、担当の福祉事務所に医療扶助の申請を行います。申請時には、指示書の他に、身分証明書や生活保護受給証明書などが必要になる場合があります。
- 医療券の交付: 福祉事務所で申請が認められると、医療券が交付されます。医療券は、指定された医療機関で医療サービスを受ける際に必要となります。
届出が必要な書類
- 訪問看護指示書: 医師が作成した原本が必要です。
- 生活保護受給証明書: 福祉事務所が発行する証明書で、生活保護を受給していることを証明します。
- 身分証明書: 運転免許証、健康保険証など、本人確認ができる書類が必要です。
- 印鑑: 申請書に押印するために必要です。
申請に必要な書類は、自治体によって異なる場合がありますので、事前に福祉事務所に確認することをおすすめします。
訪問看護ステーションの選定
訪問看護ステーションを選ぶ際には、いくつかのポイントがあります。
- 医療機関との連携: かかりつけ医や病院との連携がスムーズであることは重要です。情報共有や緊急時の対応など、連携体制が整っているか確認しましょう。
- サービス内容: 自身の病状や希望するサービス内容に対応しているか確認しましょう。例えば、特定の疾患に特化した看護や、リハビリテーションに力を入れているステーションなどがあります。
- 訪問時間: 自身の生活リズムに合わせて、訪問時間を選べるか確認しましょう。早朝や夜間の訪問に対応しているステーションもあります。
- スタッフの質: 看護師や理学療法士などの資格や経験、人柄なども考慮しましょう。信頼できるスタッフがいるステーションを選ぶことが大切です。
- 料金: 医療扶助の対象となる範囲や、自己負担が発生する場合について確認しましょう。事前に見積もりを出してもらうことをおすすめします。
複数のステーションを比較検討し、自分に合ったステーションを選びましょう。見学や体験訪問などを利用して、実際にステーションの雰囲気やスタッフの対応を確認することも有効です。
生活保護受給者の訪問看護料金
医療扶助の範囲
生活保護受給者が訪問看護を利用する場合、料金は原則として医療扶助によって賄われます。医療扶助は、生活保護法に基づいて、必要な医療サービスを受けるための料金を支給する制度です。訪問看護料金も医療扶助の対象となるため、自己負担なしでサービスを受けることができます。
医療扶助の範囲は、以下の通りです。
- 訪問看護基本療養費: 訪問看護ステーションが提供する基本的な看護サービスに対する料金です。
- 交通費: 訪問看護ステーションのスタッフが自宅まで訪問する際の交通費です。
- その他: 衛生材料費や、特別な医療材料費などが含まれる場合があります。
ただし、医療扶助の対象となるのは、指定医療機関で提供されるサービスに限られます。 (参考:東京都福祉局 - 生活保護法による医療扶助・介護扶助) 指定医療機関とは、生活保護法に基づいて、医療扶助による医療サービスを提供することが認められた医療機関のことです。訪問看護ステーションが指定医療機関であるかどうかは、事前に確認しておきましょう。
自己負担が発生する場合
原則として、生活保護受給者は医療扶助により訪問看護料金を自己負担する必要はありません。しかし、例外的に自己負担が発生する場合があります。
- 医療扶助の範囲外のサービス: 医療扶助の対象とならない特別なサービスを希望する場合、自己負担が発生することがあります。例えば、保険適用外の医療材料を使用する場合や、特別なリハビリテーションプログラムを受ける場合などです。
- 限度額を超えた利用: 訪問看護の利用回数や時間数には、上限が設定されている場合があります。上限を超えてサービスを利用する場合、自己負担が発生することがあります。
自己負担が発生するかどうかは、事前に訪問看護ステーションや福祉事務所に確認しておくことが大切です。自己負担が発生する場合は、その金額や支払い方法についても確認しておきましょう。
補足
医療扶助の範囲や自己負担については、自治体によって異なる場合があります。詳細については、必ずお住まいの地域の福祉事務所に確認してください。
その他の料金
生活保護受給者が訪問看護を利用する際、原則として医療扶助で料金が賄われますが、場合によってはその他の料金が発生することがあります。これらの料金は、医療扶助の対象外となるため、自己負担となる可能性があります。
- 特別な医療材料費: 通常の訪問看護で使用する医療材料以外の、特別な医療材料が必要となった場合、その料金が発生することがあります。例えば、特殊な創傷被覆材や、高度な医療機器を使用する場合などが該当します。これらの材料費は、事前に訪問看護ステーションから説明を受け、同意を得る必要があります。
- 交通費(例外的な場合): 通常、訪問看護ステーションの交通費は医療扶助の対象となりますが、例外的に対象外となる場合があります。例えば、訪問看護ステーションの所在地から著しく遠方にある自宅への訪問や、公共交通機関を利用できない時間帯の訪問などが該当します。この場合、事前に福祉事務所に相談し、交通費の支給が認められるかどうか確認する必要があります。
- 文書料: 訪問看護に関する診断書や証明書などの文書が必要になった場合、文書料が発生することがあります。これらの文書料は、医療扶助の対象外となるため、自己負担となります。
これらのその他の料金が発生する可能性があることを理解しておきましょう。不明な点がある場合は、訪問看護ステーションや福祉事務所に確認することが重要です。
訪問看護の回数と時間
訪問看護の利用にあたっては、訪問回数や訪問時間に制限がある場合があります。これらの制限は、医療保険や介護保険の種類、利用者の状態、医師の指示などによって異なります。生活保護受給者の場合、医療扶助の範囲内で訪問看護を受けることになりますが、適切な回数と時間を確保するために、事前に確認しておくことが大切です。
訪問回数の上限
訪問看護の回数には、原則として上限が設けられています。医療保険の場合、疾患や状態によって回数制限が異なります。例えば、末期の悪性腫瘍の患者や、精神科訪問看護指示書が出ている患者などは、週に複数回の訪問が認められる場合があります。一方、介護保険の場合は、要介護度に応じて利用できるサービスの上限額が定められており、その範囲内で訪問看護の回数を調整する必要があります。
生活保護受給者の場合、医療扶助の範囲内で訪問看護を受けることになります。訪問回数については、医師の指示に基づいて、福祉事務所が判断します。必要な回数を確保するためには、医師と相談し、適切な指示書を作成してもらうことが重要です。
訪問時間の目安
訪問看護の訪問時間も、利用者の状態やサービス内容によって異なります。一般的には、1回の訪問時間は30分から1時間程度が目安となります。ただし、状態が不安定な場合や、特別な処置が必要な場合は、より長い時間の訪問が必要となることもあります。
訪問時間については、訪問看護ステーションと相談し、自身の状態や希望に合わせて調整することができます。また、生活保護受給者の場合、医療扶助の範囲内で訪問時間も考慮する必要があります。必要な時間を確保するために、事前に福祉事務所に相談し、確認しておくことが大切です。
例外的な対応
訪問看護の回数や時間には原則として上限がありますが、例外的な対応が認められる場合があります。例えば、急な病状の変化や、緊急の処置が必要な場合などです。このような場合、訪問看護ステーションは、医師の指示に基づいて、臨時の訪問や時間延長などの対応を行うことがあります。
生活保護受給者の場合、例外的な対応が必要となった場合でも、医療扶助の範囲内で対応できる場合があります。まずは、訪問看護ステーションに相談し、必要な対応について検討してもらいましょう。その後、福祉事務所に連絡し、医療扶助の適用について確認することが重要です。
訪問看護に関する注意点
訪問看護を安心して利用するためには、いくつかの注意点があります。これらの注意点を守ることで、より効果的な訪問看護を受けることができ、トラブルを避けることができます。
- 訪問看護計画の確認: 訪問看護ステーションは、利用者の状態や希望に基づいて、訪問看護計画を作成します。計画の内容をしっかりと確認し、不明な点や希望があれば、遠慮なく伝えることが大切です。
- サービス内容の確認: 訪問看護ステーションが提供するサービス内容を事前に確認しておきましょう。自身の状態に必要なサービスが提供されているか、また、提供されるサービスの内容や手順について理解しておくことが重要です。
- 緊急時の連絡先: 緊急時に連絡できる連絡先を、訪問看護ステーションから教えてもらいましょう。夜間や休日など、通常の訪問時間外でも連絡できる連絡先を確認しておくことで、安心して療養生活を送ることができます。
- 個人情報の保護: 訪問看護ステーションは、利用者の個人情報を適切に管理する義務があります。個人情報の取り扱いについて確認し、不安な点があれば、遠慮なく質問しましょう。
- 苦情や相談: 訪問看護サービスに不満がある場合や、困ったことがあれば、訪問看護ステーションに相談しましょう。問題解決に向けて、積極的にコミュニケーションを取ることが大切です。
これらの注意点を守り、訪問看護ステーションとの良好な関係を築くことで、より質の高い訪問看護を受けることができます。
医療券の利用
生活保護を受けている方が医療機関を受診する際には、原則として医療券が必要です。訪問看護の場合も同様で、医療扶助を利用してサービスを受けるためには、医療券が必要となります。医療券は、受診の前に福祉事務所から交付されます。
医療券には、受診者の氏名、生年月日、受診する医療機関名、受診期間などが記載されています。訪問看護を受ける際には、訪問看護ステーションに医療券を提示する必要があります。医療券がない場合、医療扶助が適用されず、自己負担で料金を支払うことになるため、忘れずに持参するようにしましょう。
医療券の有効期間は、通常1ヶ月です。継続して訪問看護を受ける必要がある場合は、毎月、福祉事務所で医療券の交付を受ける必要があります。
サービス内容の確認
訪問看護を受ける際には、事前にサービス内容をしっかりと確認することが重要です。訪問看護ステーションは、利用者一人ひとりの状態やニーズに合わせて、個別の訪問看護計画を作成します。この計画には、訪問回数、訪問時間、具体的なサービス内容などが記載されています。
訪問看護計画の内容について、訪問看護ステーションから説明を受け、不明な点や希望があれば、遠慮なく質問しましょう。また、サービス内容が自身の状態やニーズに合っているか確認することも大切です。例えば、リハビリテーションを受けたい場合は、リハビリテーションに特化した訪問看護ステーションを選ぶ、あるいは、訪問看護計画にリハビリテーションの内容を盛り込むなどの対応が必要です。
サービス内容について、十分に理解した上で、訪問看護を受けるようにしましょう。
困ったときの相談先
訪問看護を受けている中で、困ったことや不安なことがあれば、一人で悩まずに、相談できる窓口を活用しましょう。
- 訪問看護ステーション: まずは、訪問看護を担当している看護師や、訪問看護ステーションの管理者などに相談してみましょう。サービス内容に関する疑問や、体調の変化、緊急時の対応など、様々な相談に乗ってくれます。
- 福祉事務所: 生活保護を担当している福祉事務所のケースワーカーも、相談に乗ってくれます。医療扶助に関する手続きや、生活上の困りごとなど、福祉に関する相談をすることができます。
- 地域包括支援センター: 高齢者の方やその家族を対象とした相談窓口です。介護に関する相談や、医療・福祉サービスの利用に関する情報提供などを行っています。
- 医療機関: かかりつけ医や、入院していた病院の医療相談室なども、相談窓口として活用できます。病状に関する不安や、治療に関する疑問など、医療に関する相談をすることができます。
これらの相談窓口を積極的に活用し、安心して訪問看護を受けられるようにしましょう。
指定医療機関とは
生活保護法に基づき、医療扶助を行うことができる医療機関を「指定医療機関」といいます。 生活保護受給者が医療扶助を利用して医療サービスを受ける場合、原則として指定医療機関を受診する必要があります。
指定医療機関は、病院、診療所、薬局など、様々な種類の医療機関があります。訪問看護ステーションも、指定医療機関である必要があります。生活保護受給者が訪問看護を受ける場合、指定医療機関である訪問看護ステーションを選ぶようにしましょう。
指定医療機関の探し方
指定医療機関は、お住まいの自治体の福祉事務所や、医療機関の窓口で確認することができます。また、インターネットで検索することも可能です。
インターネットで検索する場合は、「〇〇市(お住まいの自治体名) 指定医療機関」などのキーワードで検索してみましょう。
受診時の注意点
指定医療機関を受診する際には、以下の点に注意しましょう。
- 医療券の提示: 受診の際に、必ず医療券を医療機関の窓口に提示しましょう。医療券がない場合、医療扶助が適用されず、自己負担で料金を支払うことになるため、忘れずに持参するようにしましょう。
- 生活保護受給者であることの告知: 受診時に、生活保護を受けていることを医療機関の窓口に伝えましょう。
- 指示書の確認: 訪問看護を受ける場合は、医師の指示書が必要となります。指示書の内容を確認し、訪問看護ステーションに伝えるようにしましょう。
- サービス内容の確認: 訪問看護を受ける前に、サービス内容や料金について、訪問看護ステーションから説明を受け、十分に理解した上で、同意するようにしましょう。
これらの注意点を守り、安心して医療サービスを受けられるようにしましょう。
訪問看護のご相談はおうちナースプリュムへ
東京都内とその周辺地域で訪問看護サービスを提供する「訪問看護ステーション おうちナースプリュム」は、皆様の在宅療養をサポートいたします。港区、目黒区、品川区、中野区を中心に、東京都内であれば幅広く対応可能です。
経験豊富な看護師が、ご自宅での療養生活を安心して送れるよう、きめ細やかな看護を提供いたします。病状の観察、服薬管理、創傷処置、リハビリテーションなど、お一人おひとりの状態に合わせたオーダーメイドの看護プランをご提案いたします。
訪問看護に関するご相談は、お問い合わせフォームまたはお電話にて承っております。どうぞお気軽にご連絡ください。